図1 1936年2月12日付 The Japan Advertiser 掲載の広告
For Your
VALENTINE
Make A Present of
Morozoff's
FANCY BOX CHOCOLATE
It conveys your thoughtfulness
in a most graceful way.
On Sale at Department Stores
and Leading Candy Stores
Mail orders
Promptly Handled
Morozoff
CHOCOLATE SHOP
Tokyo Ginza
Side street of
Matsuzakaya Store
Phone: Kyobashi 56-4339
HEAD OFFICE
5-chome Hamazoe-dori
Kobe
Tel: Hyogo 2111, 1122
|
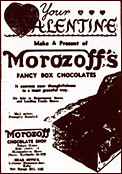
|
(山田試訳)
あなたのバレンタイン(愛しい方)にモロゾフのファンシー・ボックス・チョコレートを差し上げ
ましょう。あなたの賢明さを何よりも優雅にお伝えします。
百貨店や,有名キャンディストアで販売中
郵便でのご注文にも迅速に対応いたします
モロゾフ
チョコレート・ショップ 東京銀座 松坂屋脇入る 電話:京橋局56-4339
本社 神戸 浜添通五丁目 電話:兵庫局 2111, 1122
|
|
|